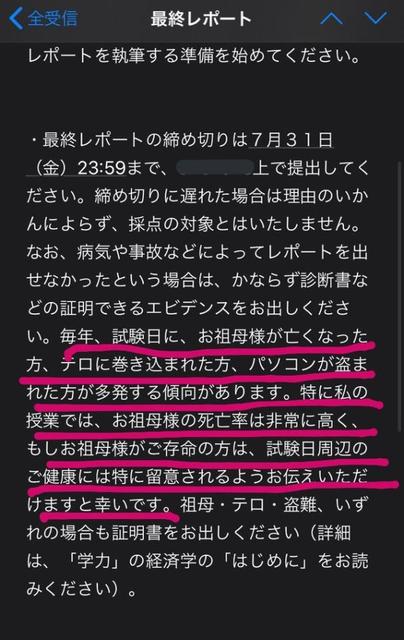永瀬正敏がコロナの時代に考えた 映画のこと仕事のこと「一層手を抜けない」
「お前たち本当によくやってくれたよなあ」。俳優デビュー作の映画『ションベン・ライダー』(1983)撮影終了後に行った銭湯で、相米慎二監督から背中越しにかけられた労いの言葉。思わず号泣してしまったあの日から早37年。俳優の永瀬正敏(54)は役者としても一観客としても、映画をずっと愛してきた。
新型コロナウイルス感染拡大の影響から、映画産業を含むエンターテインメントが一時停止を余儀なくされた。緊急事態宣言が解除され、各映画館は感染リスクを抑える対策を講じながら営業を再開。しかし平時へと戻る道のりは長い。主演作『二人ノ世界』が現在公開中の永瀬が、映画への想いと俳優としての心境を語る。
「今はどこの業種も平等に大変な時期ですから、みんなで一緒に乗り越えていかなければなりません。ミニシアターや大手シネコンも当分の間は満席にはならない状況が続くと思います。しかしそのような状況の中でも劇場を開いてくれている。映画に関わる者として感謝しかありません」と劇場関係者には頭が下がる思いだ。
映画館やそこに足を運ぶファンのために、やらなければならないことはただ一つ。「いい作品を作り続けて、お客さんが1人増えた、3人増えた、5人増えた、10人増えたという風にしていかないと申し訳がない。映画に関わる人間として一層手を抜けない。劇場に来ていただいたお客さんに喜んでもらえるような作品を、今こそ作らなければ。僕らが頑張らなければいけないんです」と力を込める。
エンターテインメントは命に関わりのない、不要不急のものだと指摘されることもある。だが永瀬は「僕個人としては今まで生きてきた中で、映画というものに何度も救われてきました。何かに躓いたり、思い悩んだりしているときに映画は心に光をくれました。これからも僕は出演者としても観客としても映画に救われていくだろうし、映画の光が消えることはないと考えています」と確信を込める。
ステイホーム期間中にもその思いは強くなった。ほとんど外出せず、自宅で映画ばかりを観る日々。「小津安二郎監督や成瀬己喜男監督の作品を観直して、なんて凄いんだ、なんて素敵なんだ、なんて凄いものを作っているんだと改めて感動。先輩方の仕事を通して、映画の光は絶対に消えないという勇気をもらいました。そして“もっと映画をやりたいな!”とも。演じたい気持ちが高ぶりました」とかつての映画青年の顔だ。
どんなピンチでも、それが大きなチャンスに転ずることだってある。「お客さんに安心して楽しんでもらえるものを作るにはどうすればいいのか。その模索はしばらく続くだろうけれど、世界中の映画人が手を取り合うだけではなく、配信、テレビ、演劇、音楽などボーダーレスに手を取り合えば、今の状況下だからこそ生み出せる新しい何かがあるはず」と期待する。
“新しい何か”のためにジャンルにとらわれることなく今後も活躍していきたい。しかしこと映画になると、新人のように背筋が伸びる思いがある。「俳優デビュー作が相米監督の映画の現場ですから、映画への思い入れはあります。しかもオヤジ(相米監督)からの評価は×と△しかもらえておらず、思わずOKと言わせるような役者になることを最終目的地点にしていました。でもそのオヤジが53歳で先に逝ってしまったので、これからも一生OKのもらえない、まあまあな役者でいるような気がしますね」。いくら作品を重ねてキャリアを積もうとも、気持ちはあの日の銭湯に置いてある。新たなことを書き込む余白はまだまだ十分ある。
(まいどなニュース特約・石井 隼人)