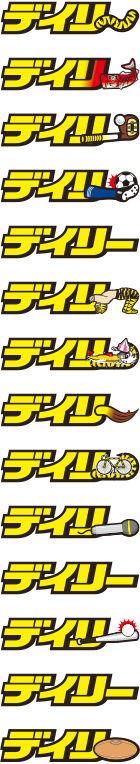小1の壁だけじゃない!入学後の試練「さんすうセット名前つけ地獄」を振り返る
ゴールデンウィークも終わり、今春入学した1年生もようやく生活のペースも落ち着いてきた。SNSで新1年生の子を持つ親たちの悲痛な声が聞こえてきた「さんすうセットの名前つけ」。実際これらは本当に使われているのだろうか。
地域や学校によって差はあるようだが、今でも一人一箱ずつ保有する学校がまだまだ多く、おはじきや数え棒、何十枚とある計算カードとあれもこれも全てに、子どもの名前を記載しなければならないのだ。
現在小学生3人の子どもを持つ筆者の場合、入学後すぐに配布され「数日以内に記名して持たせてください」と言われた。平日の日中は仕事をしているため、夜な夜なひとり地道なシール貼りとの戦いが始まった。SNSを見れば、同じく「地獄」「親の修行」「気が狂いそうになる」と言った保護者達の悲痛な叫びで溢れている。
「名前をつけるスペースが小さく、特におはじきは姓名を分けてピンセットで貼る作業が大変だった」(小1の母)と、どれだけ小さな教材でもフルネームで名前を付けるように指定されることが多く、さらに難易度が高まる要因となっている。また、「入学時に全員購入ではなく、上の子の時のをそのまま使わせて欲しかった」(小4と中2の母)と、兄弟のおさがりがあっても入学時に購入の有無の確認がなくさんすうセットを渡される場合も。
そこで疑問に思ったのが、本当に全ての教材への名前つけが必要なのか。実際に周囲の子どもを持つ多くの保護者からは低学年までで、中には一度も使用しなかった教材もあったと聞く。それでも、ひとつ残らず名前をつけるのが暗黙のルールになっている。
昭和40年代頃から小学校での活用が広まり、数の概念を理解させる目的で導入されたさんすうセット。子どもが数の概念を実際に手を動かしながら理解するために、大切な教材であることは理解している。だが今、学びの現場もデジタル化やタブレットを活用した授業が進む中で、教材の在り方にも変化が求められているのではないか。
特に今は共働き家庭も多く、限られた時間の中でこなすのはなかなか大変。一式購入が当たり前ではなく、柔軟に必要に応じて揃える選択肢が広がれば、保護者の負担もぐっと軽くなるのではないだろうか。入学は、子どもにとっても親にとっても大きな節目。新生活を気持ちよくスタートできるように、「小1の壁」だけでなく「親の壁」も少しでも低くなってくれたらとを願わずにはいられない。
(デイリースポーツ特約・はせがわ みずき)